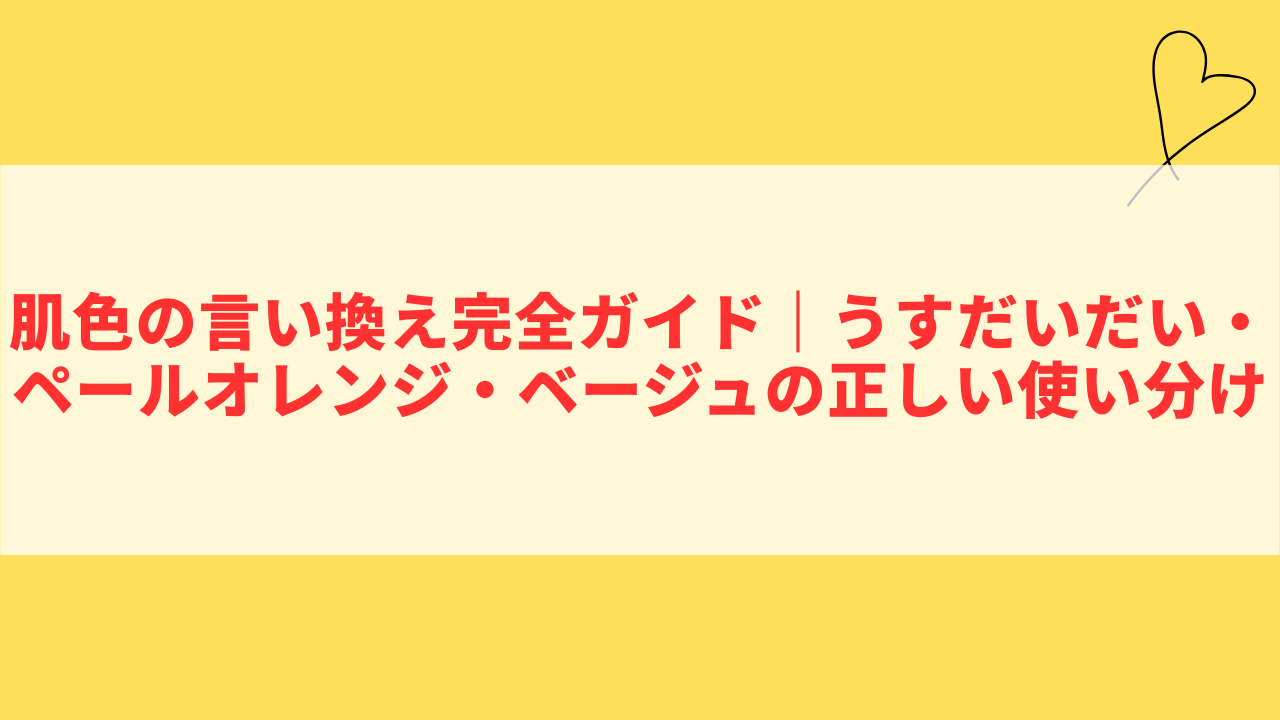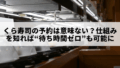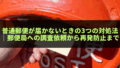かつては当たり前に使われていた「肌色」という言葉。
でも、今の時代ではその表現を見直す動きが広がっています。
この記事では、「肌色」の歴史的な背景をひもときながら、「うすだいだい」「ペールオレンジ」「ベージュ」といった言い換えの違いや意味をわかりやすく整理します。
教育現場やデザイン、子育てなど、日常の中でどんな言葉を選べばいいのか迷う場面は少なくありません。
色の名前を見直すことは、誰かを尊重するやさしい一歩です。
この記事を通して、「肌色」という言葉に込められた歴史や配慮の意味を一緒に考えてみましょう。
肌色という言葉の意味と時代背景
「肌色」という言葉は、かつて日本でごく当たり前に使われていた色名です。
でも、その背景には時代ごとの価値観や社会の前提が深く関わっています。
ここでは、「肌色」という言葉がどのように生まれ、どんな意味を持っていたのかを整理してみましょう。
かつての「肌色」が指していた色とは
「肌色」は、主に日本人の標準的な肌の色を指して使われてきた表現です。
昭和から平成初期にかけては、クレヨンや絵の具の定番カラーとして広く親しまれていました。
しかし、それはあくまで一部の人の肌色を「基準」とした色であり、すべての人を表していたわけではありません。
例えば、クレヨンの「肌色」は明るい橙色でしたが、肌の色が異なる人々にとっては「自分の肌と違う」と感じるものでした。
| 時代 | 「肌色」の使われ方 |
|---|---|
| 昭和〜平成初期 | 標準的な日本人の肌をイメージした色として定着 |
| 2000年代以降 | 多様性への配慮から使用の見直しが始まる |
「肌色」が当たり前に使われていた理由
「肌色」が特別な意味を持たずに使われていたのは、日本が比較的同質的な社会だった時代背景があります。
学校の教材や絵本、塗り絵などでは「肌色=人の顔を塗る色」として自然に受け入れられてきました。
しかし、この「当たり前」は多様な肌の色が存在するという現実を見えにくくしていたのです。
社会の変化とともに見直され始めた経緯
2000年代以降、社会に多様な文化や価値観が浸透するにつれて、「肌色」という言葉への違和感が広がっていきました。
国際交流やSNSの発展により、「誰の肌を基準にしているの?」という問いが生まれたのです。
こうした変化が、色名の見直しにつながりました。
今では、多くのメーカーや教育現場が「肌色」を別の表現に置き換えています。
| 変化の流れ | 具体的な動き |
|---|---|
| 2000年代 | 文房具メーカーが「肌色」を改名 |
| 2010年代 | 教科書・教材でも新しい表現を採用 |
なぜ「肌色」を言い換える必要があるのか
「肌色」は長く使われてきた便利な言葉ですが、現代社会ではそのまま使うことに慎重さが求められています。
ここでは、「言い換え」が必要になった背景を、多様性という視点から考えてみましょう。
多様性の時代にそぐわない理由
現代の日本では、国籍・文化・人種がかつてないほど多様化しています。
ひとつの色を「肌色」と呼ぶことは、知らず知らずのうちに「この色が普通」と決めつけることにつながる可能性があります。
つまり、言葉の選び方一つが誰かの存在を見えにくくしてしまうのです。
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 「肌色」は一色ではない | 人によって肌の色は大きく異なる |
| 一つの基準を設ける危うさ | 特定の肌色を“普通”とする偏りが生まれる |
「誰の肌色か」という問いが生まれた背景
「肌色」という言葉が再考されるようになったのは、多様性や人権への意識が高まったことが背景にあります。
特に教育現場では、子どもたちが色を通じて社会の多様性を学ぶ機会が増えました。
「肌色」という言葉を見直すことは、単なる言葉の問題ではなく他者を尊重する感性を育てることにもつながります。
身近な例で考える「言葉の影響力」
たとえば、クレヨンの箱に「肌色」と書かれていた時代、子どもたちはその色を「人の顔の色」として覚えていました。
でも、その中には「自分の肌の色と違う」と感じる子もいたはずです。
このように、何気ない言葉が「誰かを外してしまう」ことがあるからこそ、今の時代にふさわしい言葉選びが求められています。
| 昔 | 今 |
|---|---|
| 「肌色」は1つの色として教えられる | 多様な肌色を尊重する言葉に変わりつつある |
| 配慮よりも慣習が優先 | 思いやりを重視する文化へ |
「肌色」の代わりに使われている3つの色表現
ここからは、「肌色」の代わりに使われるようになった3つの色名について見ていきます。
それぞれの色には微妙な違いがあり、使われる場面や印象も異なります。
色の言い換えには単なる言葉の変更ではなく、「どんな価値観を表現するか」というメッセージも込められているのです。
「うすだいだい」―教育現場で定着した新名称
「うすだいだい(薄橙)」は、文房具メーカーのサクラクレパスが「肌色」に代わって採用した名称です。
明るくやや黄みがかったオレンジ色で、日本人の標準的な肌に近い色合いとして親しまれています。
教育現場や子どもの絵の具・クレヨンに多く使われ、今では新しいスタンダードカラーとして定着しています。
| 名称 | 色の特徴 | 主な使用場面 |
|---|---|---|
| うすだいだい | 黄みがかった明るい橙色 | クレヨン・色鉛筆・教材 |
「ペールオレンジ」―国際的でニュートラルな印象
「ペールオレンジ(pale orange)」は、英語由来の表現で「淡いオレンジ」という意味です。
ぺんてるをはじめとするメーカーが採用し、商品ラベルやカラーチャートでよく見かけます。
「うすだいだい」と色味はほぼ同じですが、英語表記にすることで国際的で柔らかい印象を与えるのが特徴です。
| 名称 | 色味の傾向 | 印象 |
|---|---|---|
| ペールオレンジ | 淡いオレンジ色 | ナチュラル・スタイリッシュ |
「ベージュ」―日常生活になじむ自然な色味
「ベージュ」はフランス語に由来する色名で、灰みがかった薄い茶色を指します。
ファッションやコスメの世界では定番中の定番で、「ライトベージュ」「ピンクベージュ」などのバリエーションも豊富です。
この色名は、肌の色を直接的に指さずとも「自然」「落ち着き」といったイメージを伝えられるのが魅力です。
| 名称 | 色の特徴 | よく使われる場面 |
|---|---|---|
| ベージュ | やや灰色がかった薄茶色 | ファッション・コスメ・インテリア |
3色の違いを比較する早見表
ここで、3つの色の特徴を一覧で整理してみましょう。
| 色名 | 色味の特徴 | 印象 | 主な使用シーン |
|---|---|---|---|
| うすだいだい | 黄みがかった明るい橙色 | やさしく親しみやすい | 教材・文房具 |
| ペールオレンジ | うすだいだいに近い淡い橙色 | 国際的・ナチュラル | 商品名・色見本 |
| ベージュ | 灰みを帯びた淡い茶色 | 自然・上品 | コスメ・衣料・デザイン |
どの色も「肌色」の代わりとして正しいわけではなく、文脈に合わせて選ぶのが大切です。
たとえば、教育の場では「うすだいだい」、商品デザインでは「ペールオレンジ」、ファッションなら「ベージュ」といったように使い分けると自然ですね。
「肌色」という言葉が歩んできた歴史
「肌色」という表現は、時代ごとに意味を変えながら使われてきました。
その背景を知ると、なぜ今の社会で見直されているのかがより深く理解できます。
ここでは、江戸時代から現代までの変遷をたどっていきましょう。
江戸時代の「宍色」とその由来
「肌色」が登場する前、日本では「宍色(ししいろ)」という表現が使われていました。
「宍」は動物の肉を意味し、淡い橙色を指していました。
しかし、徳川綱吉の「生類憐れみの令」以降、動物を連想させる言葉が避けられるようになり、「宍色」は次第に使われなくなっていきます。
その代わりとして登場したのが人を連想させる「肌色」という表現でした。
| 時代 | 色名 | 意味・背景 |
|---|---|---|
| 江戸時代以前 | 宍色 | 動物の肉の色。淡い橙色 |
| 江戸中期〜 | 肌色 | 人の肌を表す穏やかな表現として定着 |
戦後の標準化と「肌色」の定着
戦後、日本では絵の具やクレヨンが一般家庭に広がり始めました。
その中で「肌色」は、人の顔や手を塗る色として標準的に採用されます。
昭和後期には学校教育の中でも「肌色」という名称が当然のように使われ、誰も疑問を持たなかった時代でした。
| 年代 | 社会的背景 | 色の扱い |
|---|---|---|
| 1950〜1980年代 | 高度経済成長期・教育の標準化 | 「肌色」が全国的に普及 |
世界的な言葉の見直しと日本への影響
20世紀後半になると、海外で「flesh(肌色)」という言葉が人種的偏りを持つと問題視され始めました。
アメリカでは、クレヨンの色名が「peach(ピーチ)」などに変更され、多様性への配慮が進みます。
その流れは日本にも届き、2000年代以降、文房具メーカーや教育現場で「肌色」の改名が相次ぎました。
この変化は単なる言葉の置き換えではなく、社会が他者を尊重する方向へ進んだ象徴的な出来事といえます。
| 時期 | 主な出来事 |
|---|---|
| 1950〜60年代 | アメリカで「flesh」→「peach」へ改名 |
| 2000年代 | 日本でも「肌色」→「うすだいだい」「ペールオレンジ」へ |
色の言葉は、時代の価値観を反映する「文化の鏡」とも言えます。
だからこそ、今の時代に合った表現へと変えていくことが大切なのです。
教育・子育てで気をつけたい色の伝え方
「肌色」という言葉の言い換えは、大人だけの問題ではありません。
子どもたちは、日々の会話や教材を通して言葉を覚え、世界を理解していきます。
だからこそ、教育や家庭の中で「色の伝え方」に少しだけ意識を向けることが大切です。
子どもに「肌色ってなに?」と聞かれたときの答え方
もしお子さんから「この色は肌色?」と聞かれたら、どう答えますか?
そんなときは、「人の肌の色は色々あるけど、これは『うすだいだい』って言うんだよ」と説明してみてください。
「肌色=ひとつの色」ではなく、「肌色はたくさんある」という考え方を伝えることがポイントです。
色を通して「みんな違っていい」という感覚を自然に育むことができます。
| 子どもの質問 | おすすめの返答例 |
|---|---|
| 「これって肌色?」 | 「人の肌の色は色々あるけど、これは『うすだいだい』って名前の色だよ」 |
| 「なんで肌色って言わないの?」 | 「みんなの肌は少しずつ違うから、ひとつの色じゃ表せないんだよ」 |
学校・教材での言い換えの実例
教育現場でも、「肌色」の見直しが進んでいます。
たとえば、サクラクレパスは「うすだいだい」、ぺんてるは「ペールオレンジ」と改名。
小学校の図画教材や教科書でも、新しい色名がすでに使われています。
これらの変更は単なる名称の置き換えではなく、多様性を尊重する教育への第一歩でもあります。
| メーカー・教材 | 旧表現 | 新しい色名 |
|---|---|---|
| ぺんてる | 肌色 | ペールオレンジ |
| サクラクレパス | 肌色 | うすだいだい |
| 小学校教材 | 肌色 | うすだいだい・ペールオレンジ |
言葉を通して育む「多様性への感性」
子どもたちは、大人の言葉遣いから多くを学びます。
だからこそ、色の名前ひとつにも思いやりのある言葉選びが大切です。
「この言葉を使って誰かが嫌な思いをしないだろうか?」という視点を持つだけで、日常の会話がやさしく変わります。
言葉は子どもたちにとっての「社会の鏡」です。
大人が丁寧な表現を心がけることで、次の世代にも自然と配慮の感覚が伝わっていきます。
| 意識したいポイント | 解説 |
|---|---|
| 多様性を前提に話す | 「いろんな肌の色がある」と伝える |
| 言葉で差をつくらない | 「普通」「特別」などのラベルを避ける |
まとめ|「肌色 言い換え」が教えてくれる大切なこと
ここまで、「肌色」という言葉の背景や言い換えの広がりについて見てきました。
最後に、この記事で伝えたい3つのポイントを整理します。
言葉は時代とともに変わる
かつて当たり前だった「肌色」という表現も、時代の変化とともに意味を変えてきました。
言葉は固定されたものではなく、社会の価値観を映す鏡のような存在です。
大切なのは、「変わること」そのものを前向きに受け止める姿勢です。
| 昔 | 今 |
|---|---|
| 「肌色」は一つの基準だった | 多様性を尊重する複数の表現に変化 |
「正解」よりも「配慮」が大切な理由
「肌色」を言い換えるべきかどうかには、明確な正解はありません。
けれど、「この言葉で誰かが嫌な気持ちにならないかな?」と考えることこそが、今の時代に必要な感性です。
その小さな配慮が、誰かを思いやる文化を少しずつ広げていきます。
| 考え方 | 行動のヒント |
|---|---|
| 完璧を目指さない | 相手の立場を考えて言葉を選ぶ |
| 変化を恐れない | より良い言葉を探し続ける |
やさしい言葉選びが未来をつくる
言葉は、社会を映す鏡であり、未来を形づくる道具でもあります。
「肌色」の見直しは、その一例にすぎません。
私たち一人ひとりが、日常の中で言葉を少しずつ見直すこと。
それが、より包摂的でやさしい社会を育てていく第一歩になるのです。
| キーワード | メッセージ |
|---|---|
| 多様性 | 「違い」を前提に考える |
| 配慮 | 誰も排除しない言葉選び |
| 未来 | 次の世代へやさしさを受け継ぐ |