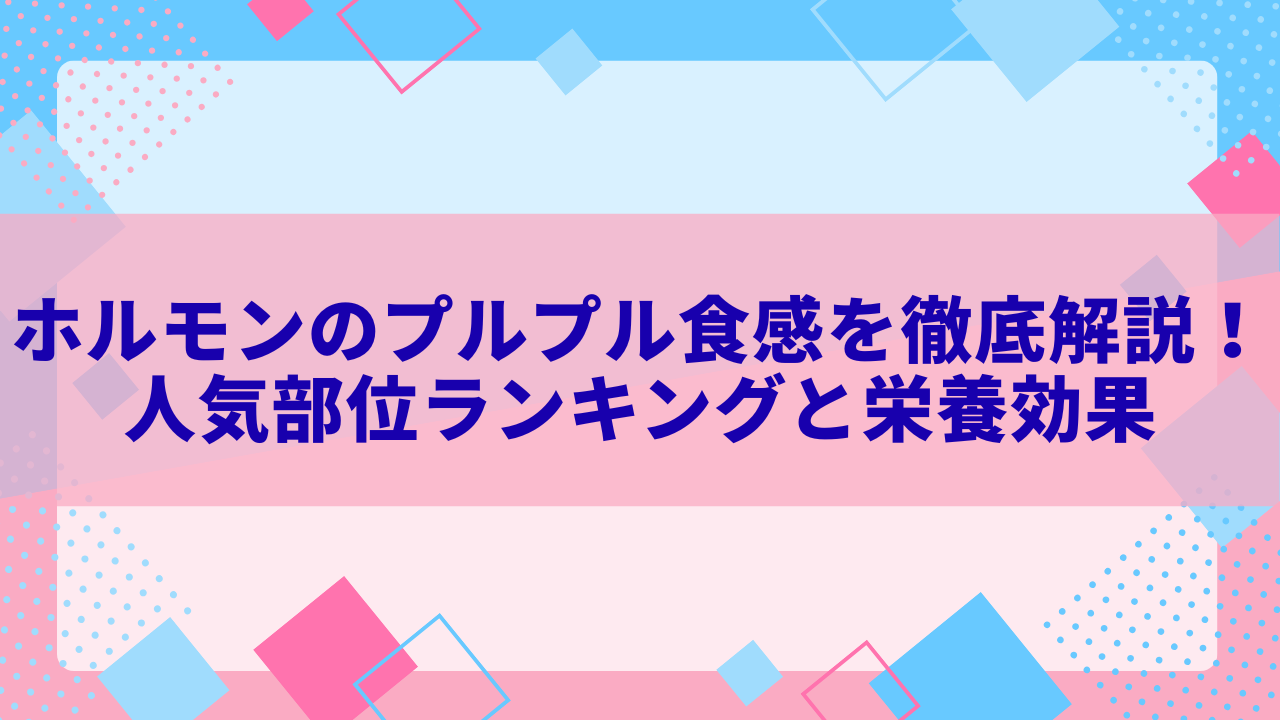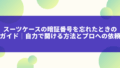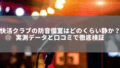焼肉やもつ鍋で出てくるホルモン。
一口食べた瞬間に広がるあのプルプル食感に、「どの部位なんだろう?」と気になったことはありませんか。
実はホルモンには、小腸・大腸・胃などさまざまな部位があり、それぞれに独自の食感と味わいがあります。
この記事では、ホルモンのプルプル感を生み出す部位の特徴をわかりやすく解説。
さらに、人気部位ランキングやカロリー比較、栄養効果までまとめました。
家庭で美味しく楽しむための焼き方や鮮度の見極め方、簡単レシピも紹介しているので、読み終わった後は「次はこの部位を食べてみよう」と思えるはずです。
焼肉店で自信を持って注文できるようになりたい方や、ホルモンをもっと楽しみたい方はぜひチェックしてみてください。
ホルモンのプルプルした部位とは?
ホルモンを食べていると、「このプルプルはどこの部分なんだろう?」と思ったことはありませんか。
実はこの食感には、ホルモン特有の構造と成分が深く関わっています。
ここではまず、ホルモンの基本と、プルプル食感の理由を解説していきます。
ホルモンの定義と基本部位
ホルモンとは、牛や豚の内臓部分の総称で、日本の焼肉や鍋料理には欠かせない食材です。
「ホルモン」という言葉の由来は「放るもん(捨てるもの)」から来ていますが、今では貴重な美味しさと栄養を持つ部位として人気があります。
代表的な部位には、小腸・大腸・胃・肝臓・心臓などがあり、それぞれ食感や味わいが大きく異なるのが特徴です。
| 部位 | 特徴 |
|---|---|
| 小腸(マルチョウ) | 脂が豊富でプルプル食感の王様 |
| 大腸(シマチョウ) | 噛みごたえと脂の甘みが魅力 |
| 胃(ハチノス・センマイなど) | 独特の見た目と歯ごたえ |
| 肝臓(レバー) | 栄養価が高く濃厚な味わい |
なぜ一部の部位はプルプルなのか?
プルプル食感の正体はゼラチン質と脂肪層です。
特に小腸や大腸にはゼラチンや脂質が多く含まれており、加熱するととろけるような食感が生まれます。
さらに、低温でじっくり火を通すことで、脂が透明になり、見た目にも食欲をそそるツヤが出るのです。
| 食感の秘密 | 理由 |
|---|---|
| プルプル | ゼラチン質と脂質の豊富さ |
| モチモチ | 皮の弾力が残るため |
| とろける | 加熱で脂が溶けるため |
人気のプルプル部位ランキング
焼肉店でホルモンを注文するとき、よく耳にするのが「マルチョウ」「シマチョウ」「テッチャン」です。
ここでは、それぞれの部位の特徴と人気の理由を紹介します。
マルチョウ(小腸)の魅力
マルチョウはプルプル食感の王様とも呼ばれる部位です。
内側に脂がたっぷり詰まっており、焼くとトロッと溶け出して口いっぱいに広がります。
タレ焼きでも塩焼きでも旨味が際立ち、脂好きの人にはたまらない選択肢です。
| 特徴 | ポイント |
|---|---|
| 脂の量 | 非常に多く濃厚 |
| 食感 | とろけるようなプルプル |
| おすすめ調理 | 塩焼き・タレ焼き両方OK |
シマチョウ・テッチャン(大腸)の違い
シマチョウは大腸のことを指し、関西では「テッチャン」と呼ばれることもあります。
マルチョウに比べると脂は控えめですが、噛むほどに甘みが広がるのが特徴です。
こってりしたタレとの相性が良く、歯ごたえを楽しみたい人におすすめです。
| 部位 | 呼び方 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大腸 | シマチョウ | 歯ごたえと脂の甘み |
| 大腸 | テッチャン(関西) | 呼び方の違いのみ |
その他の人気部位(ハチノス・センマイ・ギアラ)
プルプル以外にも、コリコリやモチモチなど独自の食感を楽しめる部位があります。
例えば、網目状の見た目が特徴のハチノス、あっさりとしたセンマイ、そして濃厚な旨味があるギアラなどです。
これらを組み合わせることで、ホルモン料理の奥深さをより実感できます。
| 部位 | 特徴 | おすすめ調理法 |
|---|---|---|
| ハチノス(第2胃) | 網目状でやわらかい | 煮込み・酢味噌和え |
| センマイ(第3胃) | コリコリとした食感 | さっぱり系の料理 |
| ギアラ(第4胃) | クセになる噛みごたえ | 煮込み・炒め物 |
ホルモンの栄養と健康効果
ホルモンは「美味しいだけの食材」ではありません。
実は、体にうれしい栄養素がたっぷり含まれているんです。
ここでは、プルプル食感を生み出す成分や、健康に役立つ栄養素について解説します。
プルプル食感を生むコラーゲンの働き
ホルモンのプルプル感の正体はコラーゲンです。
コラーゲンはたんぱく質の一種で、加熱するとゼラチンに変化し、あの独特の食感を生み出します。
また、コラーゲンは肌のハリや関節の柔軟性を保つ役割もあり、美容や健康に良いとされています。
| 成分 | 働き |
|---|---|
| コラーゲン | 肌・関節をサポート |
| ゼラチン | 消化にやさしくプルプル食感を演出 |
ビタミン・ミネラルの豊富さ
ホルモンはビタミンB群や鉄分、亜鉛などが豊富に含まれています。
これらは日々の生活で不足しがちな栄養素で、体を元気に保つために重要です。
特に鉄分は貧血予防に役立ち、亜鉛は免疫力をサポートします。
| 栄養素 | 効果 |
|---|---|
| ビタミンB群 | 代謝を助け、疲労回復 |
| 鉄分 | 貧血予防、血流改善 |
| 亜鉛 | 免疫力の維持、味覚を正常に保つ |
食べ過ぎに注意したい理由
栄養豊富なホルモンですが、脂質も多いため食べ過ぎは注意が必要です。
特にマルチョウなど脂の多い部位は、摂りすぎると中性脂肪やコレステロールが増える原因になります。
1回の目安は100g前後にとどめ、野菜と組み合わせるのがおすすめです。
| 注意点 | ポイント |
|---|---|
| 脂質の多さ | 摂りすぎると生活習慣病のリスク |
| 塩分 | タレでの過剰摂取に注意 |
| 摂取量 | 100g前後を目安にバランスよく |
部位ごとのカロリーと脂質比較
ホルモンは部位によって脂質やカロリーが大きく異なります。
ここでは代表的な部位を比較し、自分に合った選び方を紹介します。
小腸と大腸のカロリーの違い
小腸(マルチョウ)は脂がたっぷりで、100gあたり約350kcalになることもあります。
一方、大腸(シマチョウ)は脂が控えめで、約250kcal程度にとどまります。
脂のプルプル感を楽しみたいならマルチョウ、さっぱりと食べたいならシマチョウがおすすめです。
| 部位 | カロリー(100g) | 特徴 |
|---|---|---|
| 小腸(マルチョウ) | 約350kcal | 脂が多く濃厚 |
| 大腸(シマチョウ) | 約250kcal | 噛みごたえがあり比較的ライト |
ヘルシーに楽しむための工夫
ホルモンを美味しく、そしてヘルシーに楽しむためには食べ合わせがポイントです。
野菜や豆腐と一緒に調理すると、脂のバランスが整い、栄養もよりバランスよく摂取できます。
また、タレではなく塩やレモンで味付けすることで、カロリーを抑えながら素材の旨味を楽しめます。
| 工夫 | 効果 |
|---|---|
| 野菜と合わせる | 脂を中和し栄養バランスが良くなる |
| 塩・レモンで食べる | カロリー控えめでさっぱり |
| 摂取量を意識 | 食べ過ぎを防止 |
家庭でホルモンを楽しむコツ
「ホルモンは焼肉店で食べるもの」と思われがちですが、実は家庭でも十分に楽しめます。
ポイントを押さえるだけで、自宅でもお店に負けない美味しさを味わえます。
ここでは、焼き方や選び方、さらに簡単レシピを紹介します。
おうち焼肉でプルプル感を引き出す焼き方
ホルモンを家庭で焼くときは、火加減に注意するのがコツです。
強火で一気に焼くと脂が溶けすぎてしまい、プルプル感が失われます。
中火〜弱火でじっくり焼くことで、外はカリッと中はとろける理想の食感になります。
| 焼き方のポイント | 効果 |
|---|---|
| 皮面から焼く | 脂を閉じ込める |
| 中火〜弱火 | プルプル感を維持 |
| 仕上げに塩を振る | 余分な水分を飛ばし旨味アップ |
鮮度の見極め方と購入のポイント
ホルモンの美味しさは鮮度が命です。
購入時は、色や臭いをチェックするのが基本です。
透明感のある白さで、ドリップ(赤い液体)が少ないものを選びましょう。
| チェック項目 | 良い状態の特徴 |
|---|---|
| 色 | 白く透明感がある |
| ドリップ | パックにほとんど出ていない |
| 臭い | アンモニア臭がない |
簡単ホルモンレシピ(もつ鍋・マルチョウ焼き)
ホルモンは手軽に家庭料理に取り入れられます。
ここでは人気のレシピを2つ紹介します。
① もつ鍋
寒い日にぴったりの一品で、ホルモンの旨味がスープに溶け込みます。
- マルチョウ 200g
- キャベツ 1/4玉
- ニラ 1束
- にんにく・唐辛子・味噌・醤油 など
調味料でスープを作り、野菜とホルモンを煮込めば完成です。
② マルチョウのカリッと焼き
フライパンで皮面から中火で焼き、余分な脂を拭き取りながら仕上げます。
仕上げにレモンを絞れば、さっぱり食べられます。
| レシピ | ポイント |
|---|---|
| もつ鍋 | スープに旨味が溶け出す |
| マルチョウ焼き | カリッと香ばしく、レモンでさっぱり |
まとめ|自分好みのプルプル部位を見つけよう
ホルモンの魅力は、部位ごとに異なる食感と味わいにあります。
小腸(マルチョウ)の脂の甘み、大腸(シマチョウ)の噛みごたえ、胃の独特な歯ごたえなど、選び方次第で楽しみ方は無限大です。
さらにコラーゲンやビタミンなどの栄養も豊富で、美容や健康にも嬉しい効果があります。
ただし食べ過ぎには注意しながら、野菜や豆腐と組み合わせて楽しむのがポイントです。
焼肉店でも家庭でも、ぜひいろんな部位を試して、自分好みの「プルプル」を見つけてみてくださいね。
| 部位 | 特徴 | おすすめシーン |
|---|---|---|
| マルチョウ | 脂たっぷりでプルプル感抜群 | 焼肉・もつ鍋 |
| シマチョウ | 噛みごたえと甘み | 濃厚タレ焼き |
| ハチノス・センマイ | 独特の歯ごたえ | 煮込み・酢味噌和え |